小売業では、値札の張り替え作業がネックになりやすく、ミスが発生するとレジでのトラブルやクレームにつながることもあります。
こうした課題を解決する手段として注目されているのが、電子ペーパーを活用した値札のデジタル化です。
本記事では、小売業における電子ペーパーの活用方法や導入メリットを詳しく解説します。
導入によって業務の効率化やコスト削減を実現できる可能性があるため、値札管理の負担を軽減したい方には役立つでしょう。
Table of Contents

上記でかんたんに述べましたが小売業では、値札の管理には多くの手間がかかります。
価格変更のたびに手作業で張り替える必要があり、作業に時間を取られることが課題です。また、手作業ゆえにヒューマンエラーが発生しやすく、誤った価格を表示してしまうケースもあります。
こういった小売業の課題点について詳しく解説していきます。
小売業では、頻繁な価格変更が求められます。
とくに、通販サイトとの価格競争が激しくなり、1日に何度も表示価格を変更することも珍しくありません。
しかし、従来の紙の値札を使用している場合、手作業での張り替えが必要となり、大きな負担となります。
店員は売り場を回りながら、各値札を確認し、剥がして新しいものに張り替えなければなりません。
大量の商品を扱う店舗では、この作業に数時間を要することもあります。
営業時間内に行えば接客に支障をきたし、閉店後ではスタッフの労働時間が延びる要因になります。
値札の変更作業では、ミスが発生しやすいです。
手作業で新しい値札を設置する際、異なる商品に誤った価格を付けてしまうケースが少なくありません。
売り場が広く、同じカテゴリーの商品が多い店舗では、張り間違いのリスクが高まります。
誤った値札のまま販売されると、レジで表示価格と異なる金額が提示されることになります。
このようなトラブルが発生すると、顧客は店舗に不信感を抱くでしょう。
クレーム対応に追われることで、業務負担も増えてしまいます。

上述した小売業での悩みを解決できる可能性のある電子ペーパーは、次のような導入メリットがあります。
それぞれ見ていきましょう。
電子ペーパーを活用すれば、値札の張り替え作業が不要になります。
価格変更はシステム上で一括管理でき、すべての値札を一斉に更新可能です。
人手をかけることなく、リアルタイムで価格が反映されます。
価格の変更作業にかかる時間が短縮されることで、スタッフは接客や売り場の管理に集中できます。
長時間の張り替え作業が不要になることで、従業員の負担も減り、労働環境の改善にもつながるでしょう。
システム上で価格を一括管理でき、登録した価格が自動的に更新されるため、人的ミスのリスクが大幅に減少します。
クレーム対応の負担も軽減され、スタッフは本来の業務に集中できるようになります。
顧客にとっても、表示価格の誤りがなくなることで安心して買い物ができるでしょう。
価格変更の精度が向上することで、店舗の信頼性向上にもつながります。
従来の紙の値札では、照明の反射や文字の小ささにより、見づらいと感じることがあります。
高齢の顧客や視力が低下している人にとって、価格が見にくいことは購買意欲の低下につながります。
電子ペーパーを活用した電子棚札は、高コントラストで表示され、どの角度からでも視認しやすいです。
バックライトが不要で、紙のように自然な見え方を実現できるため、目に優しいです。
価格や商品情報がはっきりと見えることで、顧客はストレスなく買い物ができます。
従来の紙の値札を使用する場合、印刷や交換に多くのコストがかかります。
新しい価格に変更するたびに、紙の値札を印刷し、スタッフが手作業で張り替えなければなりません。
用紙代やインク代だけでなく、人件費も発生するため、コスト負担も大きくなります。
電子ペーパーを導入することで、紙の値札が不要になります。
これまでかかっていた紙代やインク代、紙やインクを保管するためのキャビン代等の節約につながるでしょう。
ペーパーレス化がすすむことで、資源の無駄を削減し、企業として環境負荷の低減を意識していることの訴求にもつなげられます。
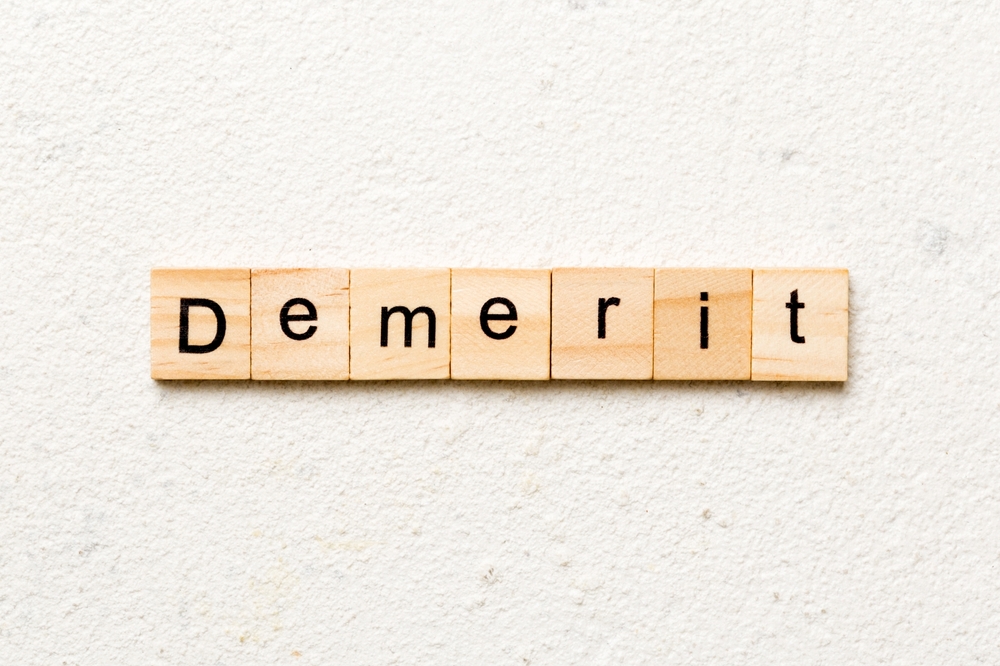
メリットがある一方で、もちろんデメリットもあります。
導入を検討する際には次のようなデメリットを踏まえて考えなければなりません。
それぞれ解説します。
電子ペーパーを導入する際、大きな初期費用が発生します。
従来の紙の値札は低コストで運用できますが、電子ペーパーは本体の購入費用やシステム構築費が必要です。
大規模な店舗では、数百枚から数千枚の電子棚札を導入することになるため、まとまった投資が求められます。
また、運用コストも考慮しなければなりません。
電子ペーパーのバッテリーは長寿命ですが、定期的なメンテナンスが必要です。
システムのアップデートや機器の故障時には、追加費用の可能性もあります。
長期的に見ると、紙の値札にかかる印刷費や人件費を削減できますが、短期間でコストを回収するのは難しいケースもあります。
電子ペーパーはディスプレイの仕様上、表示できる内容に限界があります。
一般的な電子棚札では、フルカラー表示が難しく、基本的にモノクロの表示に限定されます。
動画やアニメーションも対応しているモデルは多くありません。
価格やかんたんな商品情報を表示する用途には適していますが、販促用のカラフルなデザインや動的な広告には向いていません。
店舗のブランドイメージやプロモーション戦略によっては、紙のPOPやデジタルサイネージと併用する必要が出てきます。

小売業における電子ペーパーのメリット・デメリットについて紹介してきましたが、実際の店舗では具体的に次のような活用が考えられます。
それぞれ解説します。
まず欠かせないのが値札のデジタル化です。
従来の紙の値札とは異なり、剥がれたり汚れたりする心配がありません。
すでに解説したように、視認性に優れたディスプレイにより、どの角度からでもはっきりと価格が確認できます。
誤った値札の張り替えや価格変更ミスが発生しないため、スタッフの作業負担が軽減されるだけでなく、顧客の信頼向上にもつながります。
価格情報だけでなく、商品の詳細情報も掲載できます。
たとえば、原材料や成分、使用方法、サイズやカラーバリエーションなどについて表示できるため、顧客は比較・検討しやすくなります。
QRコードを組み合わせれば、オンライン上の詳しい情報や動画コンテンツにも誘導可能です。
たとえば、家電量販店では商品の仕様比較ページへリンクし、アパレルショップでは着用イメージ動画へリンクさせることで、顧客の購買意欲を高められます。
上述した電子ペーパーでのQRコード表示を活用すれば、商品ごとのレビューや評価を店頭で表示できます。
通販サイトでは購入前に口コミを参考にする人も多いですが、実店舗ではその場でレビューを確認するのが難しい状況です。
電子ペーパーでリアルタイムに最新のレビューを更新すれば、オンラインとオフラインの購買体験を融合させられます。
たとえば、家電量販店では「この商品の評価は4.5点」などの情報を表示してQRコードで表示すれば、購入の後押しができます。
スーパーでも「この調味料は料理研究家もおすすめ」といったコメントを掲載しつつソースのリンクを表示させておくなどが考えられるでしょう。
電子ペーパーは、店舗内の案内板としても活用できます。
フロアマップや売り場の案内、イベント情報、営業時間の変更などをデジタル表示することで、顧客にとってわかりやすい店舗環境の実現が可能です。
たとえば、最新キャンペーン情報やクーポンを表示したり、その日の特売情報やレジ待ち時間の目安をリアルタイムで更新できたりします。
紙のポスターや掲示物とは異なり、内容をかんたんに変更できるため、更新作業の手間を削減できます。

小売業で実際に電子棚札を導入する際には、以下の2つの方法があります。
それぞれの方法について詳しく解説していきます。
電子ペーパーの値札を導入する方法のひとつが、機器を購入する方法です。
サイズや種類によって価格は変わり、小型のものは手頃ですが、大型や高機能なものは高額になることが多いです。
たとえば、1000点以上の商品がある店舗では、電子ペーパー本体だけで数百万円かかることもあります。
初期費用は必要ですが、一度購入すれば長く使えるため、長期的に見ればコストをおさえられる可能性があります。
設備投資として考え、長く使うつもりなら購入がおすすめです。
電子ペーパーの値札を初期費用なしで導入したいなら、レンタルが選択肢にあがります。
一括で高額な購入費用を支払う必要がなく、月額料金だけで導入できるため、予算が限られている場合でもはじめやすいです。
不要になったときは契約を終了すればよく、撤去の手間やコストもかかりません。
まずは一部の売り場で試してから、効果を確認しつつ導入範囲を広げることも可能です。
購入よりもリスクをおさえながら導入できるため、はじめて電子ペーパーを導入する店舗にもおすすめです。

小売業で電子ペーパーの導入を図っていくならtagELがおすすめです。
tagELの特徴は下記の4点です。
それぞれについて解説していきます。
tagELならサブスクリプションプランを採用しており、初期費用はかかりません。
コストをおさえながら導入をすすめることが可能です。
定額制のため、月々の予算管理もしやすく、資金面での負担を減らしながら、効率的に導入を図る最適な選択肢です。
電子ペーパーの導入には親機や本体の購入費用が負担になりますが、tagELでは親機や本体を一部無料で提供しています(親機:1台まで、本体:10個まで)
導入前のハードルを下げ、実際の運用を試しながら導入規模を調整することが可能です。
まずは小規模にはじめて、効果を確認しながら拡大できます。
「本当に使いやすいのか」「業務に合うのか」といった不安があっても、tagELは30日間の無料トライアルを提供しており、実際の業務で試しながら導入の可否を判断できます。
無料期間中に機能や操作性を確認し、スタッフ全員で使用感をチェック可能です。リスクを最小限にしつつ、納得したうえで導入をすすめられます。
電子ペーパーをすぐに導入したい場合も、tagELならお問い合わせから最短5営業日での納品が可能です。
迅速に導入できるため、すぐに運用を開始できます。
繁忙期やキャンペーン時など、スピードが求められるシーンでも対応しやすく、業務の効率化をすぐに実現できます。
本記事では、小売業における電子ペーパーの活用方法や導入メリットについて解説してきました。
記事のポイントは下記のとおりです。
電子ペーパーの導入を検討するなら、まずは小規模に試すのが賢明です。
tagELの無料トライアルを活用し、実際の業務でその効果を確認してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ・ご相談は、こちらよりお問い合わせください。
お電話でも承っております。
お電話の際、ガイダンスが流れますので「6番(その他)」を選択し、「tagELについての問合せ」とお伝えください。
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 tagel