スタッフ数が限られる個人商店の経営では、「商品の値段変更が面倒」「手作業での更新に時間がかかる」といった悩みを抱えることが多いのではないでしょうか。
とくにセール時や価格改定の際、すべての値札を入れ替える作業は、人的ミスや労力の増加につながります。効率化の点で他店との競争に不利になるかもしれません。
本記事では、こうした課題を解決する電子ペーパー(電子棚札)の活用について解説します。また電子ペーパーの具体的な導入方法や費用、メリットについても取り上げます。
一読すれば、業務効率化しながら顧客満足度を高めるヒントが得られるでしょう。
電子ペーパーの導入は、個人商店の運営を一段と楽にし、競争力向上にもつながります。
Table of Contents

電子ペーパー電子棚札はよく混同されやすいですが、厳密には違いがあります。
ざっくり解説すると、電子ペーパーを利用した商品の一部が「電子棚札」というイメージです。それぞれの特徴についてもう少し詳しく説明します。
電子ペーパーは、紙のように自然な表示ができる省電力のディスプレイ技術です。
視認性が高く消費電力は少ないため、頻繁な情報更新が必要な場面に適しているといえるでしょう。
たとえば、スーパーマーケットでは価格表示に使用され、価格変更作業の効率化を実現しています。街中ではデジタルサイネージとして広告や案内表示にも利用されるなど、環境に配慮した省エネ表示として注目されています。
電子ペーパーはペーパーレス化や業務効率化を推進し、今後のさらなる普及が期待されている先進的技術です。
電子棚札は、電子ペーパー技術を活かしたデジタル値札で、主に小売店やスーパーマーケットで使用され、価格表示や情報更新をデジタル化するツールです。
従来の紙の値札と異なり、電子棚札なら手作業なしで情報をかんたんに変更できます。バックライト不要の省エネ設計で、視認性が高く、どの角度からでも見やすいのも特徴です。価格変更がシステム上で一括管理できれば、作業時間の大幅削減が可能ですよね。
たとえば、スーパーで500点以上の商品に導入したとすると、手動での紙値札交換と比べ、作業時間を90%以上短縮可能といわれています。
関連記事:電子棚札とは?導入のメリットや仕組みなどをまとめて紹介

スタッフ数の少ない個人商店では、価格変更や商品情報の更新作業を電子ペーパー(電子棚札)で代替すると大幅な効率アップが図れます。
代表的な活用方法としては下記3つがあげられます。
それぞれについて解説します。
電子値札を利用することで、業務効率向上と顧客満足度アップが期待できます。
紙の値札では、価格変更に手間がかかります。一方、電子ペーパーを用いた値札は、手元の端末からかんたんに価格更新が可能です。ミスや作業時間を大幅に削減できます。
たとえば、時期によって価格が変わる商品や特売品に対して値段を即座に変更でき、売れ残りの削減と売上向上が期待できます。
さらに、電子ペーパーは紙と異なり、どの角度からも読みやすく、顧客にとっても視認性が高く商品を選びやすくなる点も魅力です。
値札だけでなく商品POPとしても電子ペーパーが活躍します。
値札同様に紙のPOPでは更新作業が面倒で、商品ごとに内容を変更するのも大変です。電子ペーパーPOPなら、商品説明やキャンペーン情報をかんたんに更新でき、店内の情報を常に鮮度の高い状態にできます。
たとえば、季節限定商品や日替わり商品のアピールに活用します。また、QRコードを組み込むことで、商品説明の詳細やレシピ情報等を提供し、顧客体験を向上させることも可能です。
喫茶店や個人経営の飲食店ではメニュー表としても活用できます。
紙のメニュー表では、価格改定やメニュー更新時に手間がかかります。しかし電子ペーパーのメニュー表なら、内容を瞬時に変更することが可能です。
また店内の雰囲気にあわせて、デジタル特有のモダンさをプラスできるかもしれません。
電子ペーパーによっては食べ物の画像を掲示させたり、QRコードで成分表示ができたりもします。
柔軟なメニュー管理に加えて、店舗の魅力アップにもつながるかもしれません。
電子ペーパー(電子棚札)を導入する方法は主に下記の2種類があります。
それぞれの特徴やメリット・デメリットについて解説していきます。
まず思いつきやすいのは電子ペーパー(電子棚札)を導入時に一括して購入する方法でしょう。
電子ペーパーの価格はサイズや種類によって異なり、小型のものは1枚あたり約1,000円から、大型のものは10万円を超えるものもあります。
導入コストは高めですが、運用コストが低くなる点はメリットでしょう。後述のレンタル(サブスク)と比較し、かなりの長期で考えれば結果的にコストをおさえられる可能性があります。ただし購入の場合は、必要なサイズや枚数を慎重に考慮し、長期的な運用計画を立てることが必要です。
初期費用をおさえたい場合は、レンタル(サブスク)は有効な手段です。
購入と異なり、月額料金で利用できるため、初期投資を軽減できます。もし不要になった際でもかんたんに返却可能で、試験的な導入や段階的な拡大に適しています。
たとえば、特定の区画のみレンタルを開始することで、月々の費用を数千円~数万円におさえつつ、効果の検証が可能です。
tagELでは1枚からのレンタルプランを提供しており、手軽にお試しができます。
基幹システムと連携せずとも表示情報を更新できるため、迅速な導入が可能ですよ。
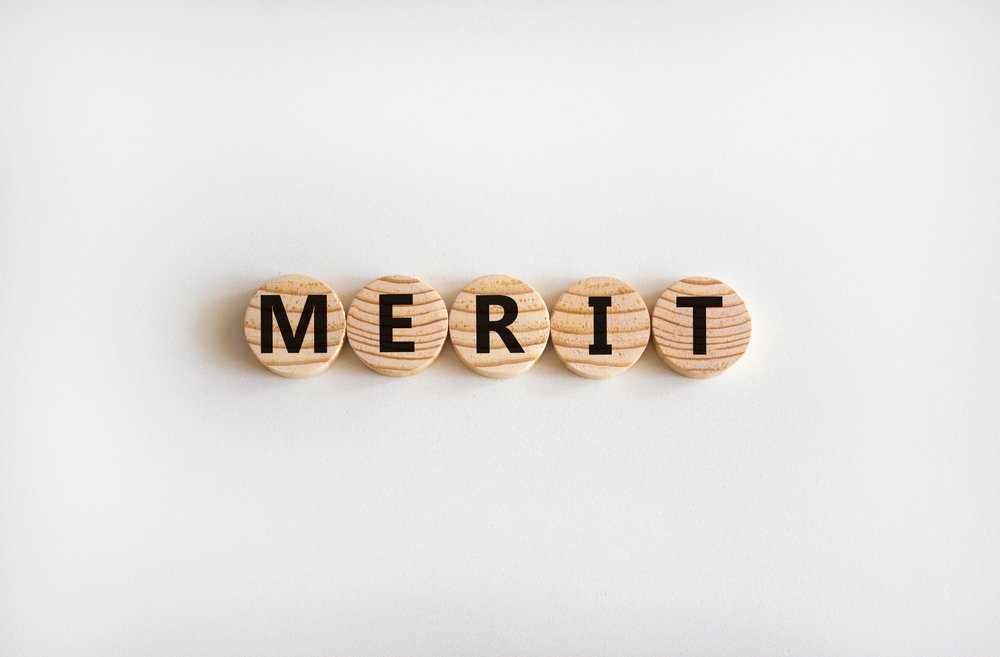
電子ペーパー(電子棚札)は個人商店においてはとくに下記の面で活躍が期待されます。
それぞれについて解説します。
電子ペーパー(電子棚札)の大きなメリットの一つは、情報の自動更新が可能になる点です。
紙では、価格や商品の情報を変更するたびに手作業が必要で、作業負担や人的ミスが発生します。しかし、電子ペーパー(電子棚札)を導入すれば、店舗の基幹システムや専用アプリを通じて、価格やキャンペーン情報を瞬時に自動更新できます。
セールや在庫調整のタイミングにあわせて迅速な対応ができ、人手が足りていない際でも販売機会の損失を防ぐことが可能です。多店舗展開の場合も、全店舗の価格を一括管理・変更できるため、統一性が保てます。
電子棚札は価格表示だけでなく、商品説明や特徴、キャンペーン情報なども記載できるため、接客中も顧客に効果的な情報提供が可能です。
たとえば、商品に「おすすめポイント」や「今月の特売情報」などを表示すれば、顧客は商品選びがしやすくなります。店員が別の接客中でも電子棚札が代わりに商品説明をしてくれるため、販売機会の損失を防げます。
また、丁寧な商品説明から顧客が店舗の細やかな配慮を感じ、満足度が向上するかもしれません。

電子ペーパー(電子棚札)を導入するメリットについて解説してきましたが、導入にあたっては上述した通り購入にしてもレンタルにしても導入コストがかかります。
しかし下記のような工夫を行うことで導入コストは最小限におさえることが可能です。
それぞれについて詳しく説明します。
価格変動の激しい商品に限定し、部分導入することがコストをおさえるのには効果的です。
全商品の値札を一度に電子棚札に置き換えると、商品数が多いほど導入コストが膨らみます。しかし、値段が頻繁に変わる商品に絞れば、電子棚札の迅速な価格変更機能を最大限に活かしつつ、費用もおさえられるでしょう。
たとえば、個人商店なら賞味期限の短い食品やセール対象品のように、価格が変わりやすいものに限定導入することが考えられます。逆に、価格が安定している商品は従来の値札でOKです。
工事費用や設置費用を最小限にする工夫も重要です。
設置やシステム設定をすべて業者に任せると、その分の人件費や工事費はかさみます。しかし自社で対応できれば、大幅なコスト削減が可能です。
たとえば、アクセスポイントの設置や棚札の設定作業は、情報システムに詳しい社員や時間を確保できるスタッフが担当することで、業者に依頼する費用はかかりません。
また、POSシステムと連携不要なモデルを選べば設定工程が簡略化され、自社内での導入がよりスムーズになるでしょう。
導入費用をおさえるには、レンタルプランがおすすめです。
先述したように購入にはまとまった初期費用がかかります。しかしレンタルなら、一度に大きな出費を避けられるため、導入時のコスト負担の大幅な軽減が可能です。
価格変動が激しい商品に対し、一時的に電子棚札を導入して効果を試す際、レンタルプランならすぐに返却できるなど、導入後のリスクを減らせるでしょう。
tagELのように無料トライアル期間を設けているサービスもあり、導入の事前に機能や使いやすさを確認したうえで、本格的な導入を検討できます。
電子ペーパー・電子棚札のお問い合わせはこちら

個人商店で電子ペーパー(電子棚札)の導入を検討するのであれば、tagELは下記の点でおすすめできます。
それぞれ詳しく解説します。
tagELは初期費用が不要です。
従来の電子棚札は高額な初期費用が障壁となることが多いです。しかしtagELは、サブスクリプション型で初期費用ゼロなため、小規模な個人店でも安心して導入できます。
1個からレンタルでき、必要な分だけ無駄なく導入が可能です。
すべての商品やメニューに一斉導入する必要はなく、気になる部分から小規模に導入できるため、コストの最適化が図れるでしょう。
小売店では「新商品」や「特売品」に、飲食店では「おすすめメニュー」の表示に使うなど、効果を確認しながら徐々に拡大できますよ。
30日間無料トライアルを活用すれば、導入前に効果をしっかり確認できます。
導入効果が不安な場合でも、無料トライアル期間中に機能を体験し、自店舗にあうかを判断できます。
tagELは納品から最短2時間で利用開始できるため、忙しい店舗でもすぐに運用ができます。
また、納品に関しても最短5営業日と短納期が可能です。
設定がシンプルでオンラインマニュアルも用意されているため、専門知識がなくても短時間で導入できる点が強みです。
効率化をすぐに実感したい個人商店や飲食店に最適といえるでしょう。
今回は個人商店における電子ペーパー(電子棚札)の活用について、メリットや導入方法などについて解説してきました。
個人商店において電子ペーパー(電子棚札)は業務効率化や顧客満足度向上に大きく貢献します。価格表示や商品情報の自動更新を可能にし、手作業の負担や人的ミスを大幅に削減できます。
導入方法としては「購入」と「レンタル(サブスク)」があり、初期費用をおさえ、安価で電子棚札を導入したい場合はレンタルがおすすめです。
tagELなら、初期費用不要で1個からレンタル可能。さらに30日間の無料トライアルがあり、最短5日と短納期で、設定後、最短2時間で利用開始できます。
コストとリスクをおさえつつ、効率的に運用がはじめられるため、個人経営の商店や飲食店に最適な選択肢です。
お問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ・ご相談は、こちらよりお問い合わせください。
お電話でも承っております。
お電話の際、ガイダンスが流れますので「6番(その他)」を選択し、「tagELについての問合せ」とお伝えください。
この記事を書いた専門家(アドバイザー)
著者情報 tagel